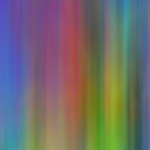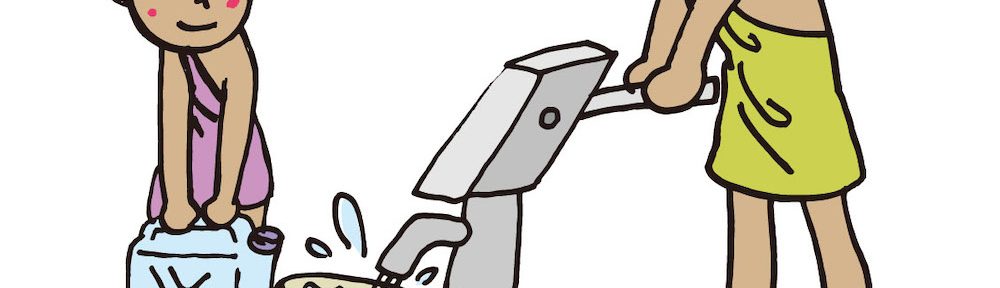
紛争の切っ掛けと問題を解決する難しさについて日本ユニセフが語る
- by gatofe
- Posted on 2019年9月29日
⒈紛争のきっかけと問題解決の難しさ
宗教や民族の違いで対立が起こる紛争は、戦争を含めて幅広い揉めごとを含む言葉です。
裁判における争いもそうですし、経済における対立でもこの言葉が使われることがあります。
ただ、多くの場合は武力をイメージするケースが少なくないので、ほぼ戦争を指すことが珍しくないです。
内戦と同義で使われることもある言葉ですから、正確に理解するのは難しいと思われます。
ジュネーヴ条約における国際人道法では、人間の尊厳を保護するべく、傷病者や捕虜の扱いなどが定義されています。
国際的性質を持たない武力によるものとされていますが、暴動レベルの問題や散発する暴力は含まれないです。
定義には反対意見を出している国もあるので、現在も明確な定義は定まっていないところです。
日本に限ると、海外で紛争レベルの争いが発生しても、戦争の名称を用いて報道するケースがあります。
政府とメディアで呼称が異なったり、論文で解釈が違っていることもあるほどです。
やはり、見る側によって捉え方が異なるので、定義の曖昧さと相まって呼び方に違いが生じるのは仕方のないことだといえるでしょう。
しかし、無政府状態に陥って異なる国や勢力が対立する構図の場合は、武力紛争と呼ばれたりします。
調停を行う機関が存在しておらず、武力で強制的な意思表示を行おうとすることが、前提条件 となっています。武力を伴わないケースでも、土地や地域レベルで争いが生じることはあります。
価値観の違いが発生の切っ掛けですが、日本だと武器が使用されることは少なく、精々暴動程度で収まる傾向です。
⒉きっかけは価値観の違いで内戦やテロが起こることがある
これは日本人に共通する価値観と、重火器があまり一般的ではないことが理由だと考えられます。
争いのレベルは大きく強度で分けられており、低強度だと政治や軍事的に睨み合っている状況です。
治安作戦や破壊工作なども行われますが、内戦に発展したりテロが起こることもあります。
中強度になると、対立状態は深刻化して行き、地域が限定される戦争状態だと評価されます。
こうなると短期間で解決するのは難しく、長期化を視野に解決策を模索する必要が出てきます。
高強度状態では、もはや単純な対立の構図ではなく、複数の国や勢力が関わっていることになります。
武力行使どころか国を挙げた総力戦であったり、最悪を想定すると核戦争も含まれるものです。
アイデンティティや生活に直結する資源や土地の奪い合いに、関係性の対立と宗教観の違い、経済バランスといったことが紛争の切っ掛けだと考えられています。
他にも、文化や民族の違いに集団心理も関係してくるので、問題が起こる理由は実に多種多様です。
自然発生的に発生することもあれば、誰かが意図的に引き起こすケースも存在します。
問題解決の基本的な考え方は、継続的にコミュニケーションを取って説得する非暴力的な方法と、暴力も辞さない暴力的な手段に分けられます。
どちらが正しいというものではなく、必要に応じて使い分けるのが基本だといえます。
⒊発生させない、長引かせない事が重要
法律的な問題の場合は、裁判で争って決着をつける手段も使えます。
一方、政治的な案件だと調停で解決を図るケースも珍しくないです。
いずれにしても、止める理由がなければ紛争は続いてしまうので、何の為に争っているか明確にしてから、具体的に納得できる着地点を模索することになります。
暴力で解決しようとすると、憎しみや怒りの連鎖を引き起こし、ますます泥沼状態を深めてしまいます。
殴り合っても疲弊するだけですし、長期化すると問題解決後に残る爪痕が大きくなるので、早めに解決するのが望ましいです。
それでも、理想と現実は思った以上に開きが大きく、継続的に解決の努力を試みても泥沼化したり、長期化して手がつけられなくなりがちです。
地域や民族レベルの争いなら、結局のところは当事者間の問題なので、国家が介入しなくても良いことになります。
ところが、人道的には無視できないので、問題が大きくなったり長引くと、少なからず関係のある国も頭を抱え始めます。
後ろで糸を引いている勢力を除き、紛争が広がって得をする人はいませんから、やはり発生させないことと長引かせない2つが重要だと分かります。
話し合いができる状況ならそれを大切に、なるべく時間を掛けてお互いに納得できるのが理想的です。
感情的になり過ぎたり、勢力を構成するメンバーが暴走すると手がつけられませんから、あくまでも冷静に対応するのが得策です。
インフラが破壊されて生活レベルが大幅に低下したり、罪のない人達が傷つき苦しむなど、武力を伴う争いは大きなダメージをもたらします。
将来ある子供が絶望することも、幸せだった家族が離れ離れになることも少なくないので、発生させないのが最もベストです。
ただし、現実には望まなくても周りの人達が争いに加担したり、短期間で急激に事態が変化することもありますから、完全にコントロールするのは不可能です。
大切なのは、前兆が見られたら軽視したり無視せず、早期に事態の収束を図ることが問題解決の原則となります。
日本ユニセフ関連記事
最終更新日 2025年5月30日
目次1 ⒈紛争のきっかけと問題解決の難しさ2 ⒉きっかけは価値観の違いで内戦やテロが起こることがある3 ⒊発生させない、長引かせない事が重要3.0.1 日本ユニセフ関連記事 ⒈紛争のきっかけと問題解決の難しさ 宗教や民族…